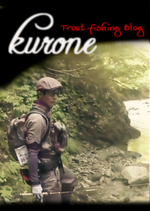2013年03月16日
前線部隊の空母
♪Joe Cocker / With a little help from my friends
ジョー・コッカー。私が「声」で鳥肌が立った(良い意味で)数少ない白人歌手の一人。
こんな声の男に生まれたかった。。
今夜は私が地味に欠かせないと思っている小物を紹介してみようと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私はどちらかというとルアーチェンジが多い方だ。
ひとつのポイントでひとつのルアーを撃ち、「なんだいないや」と思えるくらい腕に自信があれば良いのだろうが、単純な話、諦めが悪いのだ。(笑)
だから反応が得られない場合は頻繁にルアーをローテーションする。
しかしそこは一度ルアーという異物を通したポイント。魚は我々をのんびり待ってはくれない。
「さ~てお次は・・」なんてまったりワレットを出し入れしている間に、すっかり警戒心が芽生えてしまう事だってあるだろう。
だからこそ、異なるメソッドや可能性を探る為にも、ルアーチェンジはなるべく間を置かずに素早く行いたいものだ。
そのような意図の為に一般的によく使われるのがウレタンフォームやムートンのフライ用のパッチだと思う。
しかし、私はそのどちらのタイプも使ってみたのだが、当然とはいえやはりそれらは「フライ」に的を絞ったツールであり
ルアーの一時保管場所として使用するにはあまりにもデメリットが多かった。
ウレタンフォームタイプの場合、針の抜き差しのしやすさは抜群なのだがその分固定は甘く、
ルアーをぶらさげたままちょっと移動しようもんなら"川面にぽちゃん!"のリスクが激しく大きい。(実際にそれが原因で数個ロストした)
対してムートンの物は、ぶら下げた際のホールド感は素晴らしいのだが、
バーブ(返し)がしつこく絡まってしまって結果的に素早くルアーを取り外す事ができず、何のためのパッチなのかわからなくなってしまうという状況だった。
"その両方のデメリットを解消できる商品は無いのか・・・"
条件①:針刺し部はルアーを取り出しやすいウレタンフォーム
条件②:スムーズに開閉でき、尚且つ勝手に開いたりしない蓋の付いたボックスタイプで、ルアーを2~3個収納出来るスペースがあるもの
しかしいくら探せども私の理想を叶えてくれる物は見つからなかった。
そこで決心。
無いなら作っちまおう。(゚∀゚)
という事で出来上がったのがこちら、

材料は100均にある単なる名刺入れ。
実はこの計画、昨シーズン初め思いつき、去年はシムスのベストに同様の物をベルクロ方式で取付けていた。
しかしベストではなくバッグに変わった今、取り付け方法を変えなければならず新たに製作する事となったわけだ。
今回は安全ピン仕様。

大きめのピンを、可動溝を付けた二重の基盤で挟み、エポキシ接着剤にて固定。
これなら多少の力がかかっても強度的には安心。
変な文字が色々書いてあるのが気にはなるが、そこは何せ100均(笑)
裏面だし、細かいことは良しとしよう(雑)
実際に取り付けるとこんな具合。


ドロップダウンで開放したボックス部分の上部だけにウレタンフォームを取り付け、
ルアーが接触するボックス内部にはクッション性のある合皮シートを敷き詰めている。
この方式ならワンタッチで開閉出来、スムーズにルアーが取出せる。
おまけに有難い事に元々下部についている袋状のアールが不用意なルアーの遊びを軽減し、
ルアーチェンジで開放した際も不意に落としてしまう等ということもほとんど無い。
実際に去年はほぼこのボックスをベストに装着して釣りを続けたが、コレが予想以上に使い勝手が良かった。
私も含め大抵の方もきっとそうだと思うが、ワレットに様々なルアーを詰めてはいても、
フィールドで頻繁にローテーションするパターンは大体決まっている場合が多いのが実状だろう。
メインルアー、アクションの異なるルアー、レンジを変えられるルアー。
実際のところその3本があれば、結構釣りを組み立てることは出来るもの。
様々な戦術的ルアーが満載されたワレットが「本部基地」だとするならば、
このボックスは最前線で戦う優秀なルアー達の為の「空母」となる。
この空母が私にとっては非常に有難い、なくてはならない存在なのだ。
私が自作したこのボックスはあくまでも個人的な需要を具現化した物に過ぎない為、
そんなんいらんだろと思われる方も勿論多いと思う。
しかしもしもどこかに私と同じような悩みを持っている方が居られるならば、参考にして頂けると幸いだ。
簡単で、何よりお財布に優しいので(笑)
ジョー・コッカー。私が「声」で鳥肌が立った(良い意味で)数少ない白人歌手の一人。
こんな声の男に生まれたかった。。
今夜は私が地味に欠かせないと思っている小物を紹介してみようと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私はどちらかというとルアーチェンジが多い方だ。
ひとつのポイントでひとつのルアーを撃ち、「なんだいないや」と思えるくらい腕に自信があれば良いのだろうが、単純な話、諦めが悪いのだ。(笑)
だから反応が得られない場合は頻繁にルアーをローテーションする。
しかしそこは一度ルアーという異物を通したポイント。魚は我々をのんびり待ってはくれない。
「さ~てお次は・・」なんてまったりワレットを出し入れしている間に、すっかり警戒心が芽生えてしまう事だってあるだろう。
だからこそ、異なるメソッドや可能性を探る為にも、ルアーチェンジはなるべく間を置かずに素早く行いたいものだ。
そのような意図の為に一般的によく使われるのがウレタンフォームやムートンのフライ用のパッチだと思う。
しかし、私はそのどちらのタイプも使ってみたのだが、当然とはいえやはりそれらは「フライ」に的を絞ったツールであり
ルアーの一時保管場所として使用するにはあまりにもデメリットが多かった。
ウレタンフォームタイプの場合、針の抜き差しのしやすさは抜群なのだがその分固定は甘く、
ルアーをぶらさげたままちょっと移動しようもんなら"川面にぽちゃん!"のリスクが激しく大きい。(実際にそれが原因で数個ロストした)
対してムートンの物は、ぶら下げた際のホールド感は素晴らしいのだが、
バーブ(返し)がしつこく絡まってしまって結果的に素早くルアーを取り外す事ができず、何のためのパッチなのかわからなくなってしまうという状況だった。
"その両方のデメリットを解消できる商品は無いのか・・・"
条件①:針刺し部はルアーを取り出しやすいウレタンフォーム
条件②:スムーズに開閉でき、尚且つ勝手に開いたりしない蓋の付いたボックスタイプで、ルアーを2~3個収納出来るスペースがあるもの
しかしいくら探せども私の理想を叶えてくれる物は見つからなかった。
そこで決心。
無いなら作っちまおう。(゚∀゚)
という事で出来上がったのがこちら、
材料は100均にある単なる名刺入れ。
実はこの計画、昨シーズン初め思いつき、去年はシムスのベストに同様の物をベルクロ方式で取付けていた。
しかしベストではなくバッグに変わった今、取り付け方法を変えなければならず新たに製作する事となったわけだ。
今回は安全ピン仕様。
大きめのピンを、可動溝を付けた二重の基盤で挟み、エポキシ接着剤にて固定。
これなら多少の力がかかっても強度的には安心。
変な文字が色々書いてあるのが気にはなるが、そこは何せ100均(笑)
裏面だし、細かいことは良しとしよう(雑)
実際に取り付けるとこんな具合。
ドロップダウンで開放したボックス部分の上部だけにウレタンフォームを取り付け、
ルアーが接触するボックス内部にはクッション性のある合皮シートを敷き詰めている。
この方式ならワンタッチで開閉出来、スムーズにルアーが取出せる。
おまけに有難い事に元々下部についている袋状のアールが不用意なルアーの遊びを軽減し、
ルアーチェンジで開放した際も不意に落としてしまう等ということもほとんど無い。
実際に去年はほぼこのボックスをベストに装着して釣りを続けたが、コレが予想以上に使い勝手が良かった。
私も含め大抵の方もきっとそうだと思うが、ワレットに様々なルアーを詰めてはいても、
フィールドで頻繁にローテーションするパターンは大体決まっている場合が多いのが実状だろう。
メインルアー、アクションの異なるルアー、レンジを変えられるルアー。
実際のところその3本があれば、結構釣りを組み立てることは出来るもの。
様々な戦術的ルアーが満載されたワレットが「本部基地」だとするならば、
このボックスは最前線で戦う優秀なルアー達の為の「空母」となる。
この空母が私にとっては非常に有難い、なくてはならない存在なのだ。
私が自作したこのボックスはあくまでも個人的な需要を具現化した物に過ぎない為、
そんなんいらんだろと思われる方も勿論多いと思う。
しかしもしもどこかに私と同じような悩みを持っている方が居られるならば、参考にして頂けると幸いだ。
簡単で、何よりお財布に優しいので(笑)
~Fin~
2013年03月14日
年券ゲット
ついに今年も年券をゲット!
こーゆうもんに関しては無駄に動きが早い私です。
J州屋さんから電話を頂いた3分後には受け取ってました(たまたま修理車の納車で近くにいたものでw)
今年は赤ですか~♪
んん、変な色じゃなくてよかった( ´▽`)b
っていっても私の場合ぶら下げて使うわけでもないからあんまり関係無いんですけどね(笑)
あ、ヤバイ、顔がバレる・・
そんなことはさておき、
なんですかこのイカついコブラは(爆笑)
そりゃ今年はヘビ年にゃ違いありませんが何もコブラさん出さんでも・・(゜∀。)
しかも妙にリアル。。。
去年までこんなに可愛らしかったのに。
このポップさは何処へ?!(笑)
まぁそんな事を言いながら私、
漁協のこの不思議なセンス、嫌いじゃないです( ●´艸`)
あぁ。。年券を手にしたら余計に釣欲が溢れ出てきた(汗)
早う来い!春よ!!!
2013年03月12日
欲ばり男の腰回り

私の荷物は多い。
釣行を共にしたアングラーの方々と比べても、やはり私が身につけている荷物は人と比べて多いように思う。
ただでさえかさばる「魚籠」をぶら下げている私。
その上新しく仕入れたのはバックパックにチェストパック・・・おそらく今年はさながら鎧武者の様なゴテゴテとした立ち姿となる事だろう。
それに対して雑誌を開けば(キャンパーの方は別として)大抵のアングラーの方々は最低限の装備に身を包み、軽快に渓を駆け回っている姿ばかり。
「必要最低限の荷物」
それは釣りだけに留まらず、山に入る人間の基本中の基本だという事は周知の事実だ。
軽装備である事の利点は体力の消耗を抑えるばかりか、それに伴い精神的余裕から集中力が高まり、当然の事ながら釣果にまで影響する。
こんな私でさえ、渓流釣りに"軽快なフットワークは欠かせない条件"と真剣に考えている。
しかし荷物は減らせない。いや、減らさない(笑)
わかっちゃいるけど止められない♪ なんて、植木等になりたいわけでは無いのだが。
いわゆる貧乏性なのだろう。自分の中で"必要"と思っている物を省くのはなんとなくどこか落ち着かないのだ。
そんな矛盾を常に抱えている滑稽な私。
しかしこんな私だからこそ、身に付ける装備の重心の位置や、釣りに伴う円滑な動作に関しては人一倍の熟考を繰り返している自負だけはある。
・大きな装備を身に付け、無造作に転がる岩々をどうすれば軽快に駆けて行けるか。(足取りの軽さ)
・へつり、高巻き、藪こぎの際に邪魔にならない手段は確保できているか。(安全の確保)
・キャスティング、アクション、ランディング時の身体の動線をいかに遮らないように配置するか。(集中力の維持)
矛盾をまるごと抱えたまま克服するというのはなかなかに難儀なものだ。
それでも部屋の中で何度も装備を付けてはシミュレーションを繰り返し、なんとか納得のゆく装備にまとめあげた。
しかし・・・唯一どうしても誤魔化しきれないものがあった。
それは案の定、大きな魚籠(苦笑)
バックパックにチェストパックという重装備な上半身だというのに、おまけに腰にまでこのデカ物などどうしたって邪魔以外の何者でもない。
私が使用しているのはいわゆる餌師用の樹脂製クリールと呼ばれる飯盒のような形状のもの。
魚の入れやすさ、保冷性のほか、万が一の場合一時的な浮き輪代わりになったりと利点は予想以上に大きかったのだが、ベストスタイルの去年でさえ時々「腰重いな・・」と感じていたものだから、今季はさすがにどうにかしなくてはとあちこち調べていた。
そしてついに見つけたのがこちら、
Angler's House
ガーニークリール(M)
これは既に生産中止されている商品ではあるが、オークションでなんとか入手する事ができた。
この製品の仕組みとしては、保冷剤を入れて直接魚を冷やす樹脂製クリールとは違い、魚を入れた後この魚籠自体を水に浸し、主素材であるリネンに染み込んだ水分が蒸発する気化熱を利用して内部の温度を一定に保つという原始的なもの。
使い勝手や保冷効果に関してはどうしたって樹脂製の物には勝てないのだが、今回私が何より優先したのは重量と体積。
この手の魚籠は大概がショルダーバッグのように肩からかけるものしか無いのだが、これに関してはベルトループが標準装着されており、まさに私の需要と合致する唯一の商品。
見た目、素材、造りの割になかなかの価格ではあったが、これ以外無いのだからしようがないのだ。
"そんなに困るなら魚籠なんて持たなきゃいいのに?"
いやいや、それはその。今んところ意思は変わってないので、ええ(笑)
これで無事魚籠のかさばり問題も一件落着。
あとは渓に立つばかり。
(ちなみに魚籠の横に付けてるのは鉈。柄はそれっぽいが決してハンドソーではない(笑)
この変な柄のおかげで、どんなに全力で振り回しても手からすっぽ抜けることは無いので割と重宝している。)
まもなく年券が届き、9日後にはようやくこの秋田も解禁となる。
半年間待ち焦がれた解禁。。。(感涙)
とはいえ現実的な話、私も一己の会社人。
職種の関係上今月は休めそうにないので、おそらく渓に挨拶できるのは来月となる事だろう。
念の為、、ホントに念の為に、おそらく使わないまま押入れにしまう事になるような気もするが、一応こんなんも用意してみた(笑)
あぁ・・・早く魚に会いたいよぉう( 」´0`)」(哀願)
2013年03月08日
酒の話
いよいよお隣では解禁。
早々と渓への挨拶を済ませる強者方を横目に、
熱い羨望の眼差しを送りつつも未だ重い腰が上がる気配のないものぐさなくろねです。(笑)
とりあえずは腰の上がっていない今だからこその別ジャンルのテーマ。
今日は”酒の話"です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ブログタイトルからもあからさまに察して頂ける通り、私は大の酒好きである。
遺伝的に強い方ではない(寧ろ弱い)のだが、旨い酒ならジャンルを問わずどんなものでも好んで飲む。
一時はその酒好きに元来の性分である創作欲が相まって、道具を揃えてバーテンの真似事を趣味にしていた程だ。
スピリッツやリキュール等々50本ほど賑やかに部屋に並べ、血豆ができるほどステアの練習をし、
毎晩オリジナルカクテルの創作に励んだりもした。
しかしさすがにカクテルばかり飲んでいると糖分の過剰摂取で体調を崩しそうになったのできっぱりと辞め、
それからは家では専ら蒸留酒のみを飲むようになっていった。
焼酎・泡盛・ウォッカ・ラム・テキーラ・ウイスキー・ブランデー等々。。
飲むほどに蒸留酒の味わいの深さに興味は増した。
とりわけ愛着を覚えたのが"ウイスキー"。
かつての私にとって"ウイスキー"といえばキツイだけの臭い酒。
それはROCKの代名詞であり、荒々しい男らしさであり、ロクでもない飲んだくれのイメージ。
しかし、飲む程に、歴史を学ぶほどにこの"ウイスキー"への関心は膨らみ、
アルコールの強さに慣れたその先には繊細な味わいの広がりを感じる事が出来るまでになっていった。
アメリカン(バーボン)、カナディアン、ジャパニーズ、アイリッシュ、スコッチと
様々なウイスキーを飲んだ。
まさにお国柄なのだろう。それぞれの国の"ウイスキー"に対する概念や需要は驚くほど味や香りによく顕れている。
その中でも私が特に興味を注いでいるのが「スコッチ」(スコットランド産ウイスキー)。
ウイスキーの正規の発祥地はアイルランドだという説が濃厚だが、その後の創意工夫・土壌に合わせた味の追求がもたらしたグローバルな発展への貢献は紛れもなくスコットランドの実績である。
このスコッチという飲み物。
特にシングルモルト(単一麦芽)に関しては単に"ウイスキー"という単語だけでは語りきれない、ひとつの「学問」といっても差し支えないような奥深さを持っている。
同じスコットランドとはいえ地域や蒸留所によってその味わいも多種多様。

バランスが良く、花や果実を連想させる香りだちのスペイサイド。
穏やかな麦の風味が素直に表現されたローランド。
オイリーで塩っぽい、コクのある舌触りのキャンベルタウン。
絹のように滑らかで、鍛錬の末に成熟した調和を感じさせるハイランド。
強烈なピート香を伴う、海を連想させる力強い味わいを前面に押し出したアイラ。
それぞれ独立した島ならではの、個性的な表情をもつアイランズ。
どれも独創的で、どれも美味い。
私が個人的に気に入っているのは「アイラ」産のモルト。
ボウモア・カリラ・ラガヴーリン・アードベック等、アイラ島の蒸留所には他の地方とは一線を画す大きな特徴がある。
それは"燻製"とも言える強烈な「ピート香」。
ウイスキーを造る際、蒸留する過程の前に燃料を焚いて麦芽をよく乾燥させる必要がある。
その為に使われる燃料の代表格がピートなのだ。
ピートとはヘザー、コケ、シダ等の植物が数千年にわたって土壌に堆積してできた「泥炭」の事で、特にアイラ島ではよく採れるもの。
他の地方は燻製香を嫌い別の物を使用したり、ピートを焚いても少量で終わらせるのがセオリーとなっているが、アイラ島の蒸留所は島中でよく採れるそのピートをふんだんに使用し、力強い独自の味わい事を生み出すという手段を選択した。
その産物がこの素晴らしい香りである。
どの蒸留所もピーティな香りの中にそれぞれの個性的な風味を持たせているアイラ・モルトだが、
特に私が部屋に常備していないと落ち着かないのがこちら。

アイラ・モルトの中でも一段とピーティな燻製香に、荒波を思わせる強烈な磯の香り、オイリーな舌触り、口に含んだ時の甘さが特徴となっている。
正直同じウイスキー好きでも、日本のものに慣れ親しんだ方なら苦手だという方も多い。
事実、10人に7人程の割合で「薬品臭い」「飲みもんじゃねぇ」という感想を頂戴する(笑)
好きか嫌いか、こんなに瞬時に明確に分かれる酒も珍しいかもしれない。
興味のある方は是非チャレンジしてみて欲しい。
これは余談ではあるが、ウイスキー、特にスコッチを飲む際におすすめの飲み方がある。
その名も「トゥワイスアップ」。
それはニート(ストレート)に同量の水を加えたもの。
要するに1:1の水割りなのだが、この場合グラスはチューリップ型のテイスティンググラスとなる。
ニートだとどうしてもアルコールのツンとした匂いが鼻に突き、香りを楽しむというよりも舌触りや味覚でのテイスティングとなってしまうのだが、スコッチの魅力はその"香り"の豊かさにある。
トゥワイスアップではその香り立ち、温度による変化までをも存分に楽しむ事ができるのだ。
バーボンのようにキレのある力強い香りの酒はロックにしてもその持ち味は変わる事は無いが、
スコッチの持つ繊細さを味わう事をしないのは本当に勿体無い。(値段も高いしw)
もしバーに行く機会があったら、是非この飲み方を試してみて欲しい。
その一杯で"ウイスキー"のイメージが変わる可能性も少なくは無いと思う。
P.S.
ちなみに居酒屋や"なんちゃって"バーで
「トゥワイスアップで!」なんて気取って言うと
「えっ?・・・・・なんですか?」と、赤っ恥をかくので注意が必要だ(笑)

早々と渓への挨拶を済ませる強者方を横目に、
熱い羨望の眼差しを送りつつも未だ重い腰が上がる気配のないものぐさなくろねです。(笑)
とりあえずは腰の上がっていない今だからこその別ジャンルのテーマ。
今日は”酒の話"です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ブログタイトルからもあからさまに察して頂ける通り、私は大の酒好きである。
遺伝的に強い方ではない(寧ろ弱い)のだが、旨い酒ならジャンルを問わずどんなものでも好んで飲む。
一時はその酒好きに元来の性分である創作欲が相まって、道具を揃えてバーテンの真似事を趣味にしていた程だ。
スピリッツやリキュール等々50本ほど賑やかに部屋に並べ、血豆ができるほどステアの練習をし、
毎晩オリジナルカクテルの創作に励んだりもした。
しかしさすがにカクテルばかり飲んでいると糖分の過剰摂取で体調を崩しそうになったのできっぱりと辞め、
それからは家では専ら蒸留酒のみを飲むようになっていった。
焼酎・泡盛・ウォッカ・ラム・テキーラ・ウイスキー・ブランデー等々。。
飲むほどに蒸留酒の味わいの深さに興味は増した。
とりわけ愛着を覚えたのが"ウイスキー"。
かつての私にとって"ウイスキー"といえばキツイだけの臭い酒。
それはROCKの代名詞であり、荒々しい男らしさであり、ロクでもない飲んだくれのイメージ。
しかし、飲む程に、歴史を学ぶほどにこの"ウイスキー"への関心は膨らみ、
アルコールの強さに慣れたその先には繊細な味わいの広がりを感じる事が出来るまでになっていった。
アメリカン(バーボン)、カナディアン、ジャパニーズ、アイリッシュ、スコッチと
様々なウイスキーを飲んだ。
まさにお国柄なのだろう。それぞれの国の"ウイスキー"に対する概念や需要は驚くほど味や香りによく顕れている。
その中でも私が特に興味を注いでいるのが「スコッチ」(スコットランド産ウイスキー)。
ウイスキーの正規の発祥地はアイルランドだという説が濃厚だが、その後の創意工夫・土壌に合わせた味の追求がもたらしたグローバルな発展への貢献は紛れもなくスコットランドの実績である。
このスコッチという飲み物。
特にシングルモルト(単一麦芽)に関しては単に"ウイスキー"という単語だけでは語りきれない、ひとつの「学問」といっても差し支えないような奥深さを持っている。
同じスコットランドとはいえ地域や蒸留所によってその味わいも多種多様。

バランスが良く、花や果実を連想させる香りだちのスペイサイド。
穏やかな麦の風味が素直に表現されたローランド。
オイリーで塩っぽい、コクのある舌触りのキャンベルタウン。
絹のように滑らかで、鍛錬の末に成熟した調和を感じさせるハイランド。
強烈なピート香を伴う、海を連想させる力強い味わいを前面に押し出したアイラ。
それぞれ独立した島ならではの、個性的な表情をもつアイランズ。
どれも独創的で、どれも美味い。
私が個人的に気に入っているのは「アイラ」産のモルト。
ボウモア・カリラ・ラガヴーリン・アードベック等、アイラ島の蒸留所には他の地方とは一線を画す大きな特徴がある。
それは"燻製"とも言える強烈な「ピート香」。
ウイスキーを造る際、蒸留する過程の前に燃料を焚いて麦芽をよく乾燥させる必要がある。
その為に使われる燃料の代表格がピートなのだ。
ピートとはヘザー、コケ、シダ等の植物が数千年にわたって土壌に堆積してできた「泥炭」の事で、特にアイラ島ではよく採れるもの。
他の地方は燻製香を嫌い別の物を使用したり、ピートを焚いても少量で終わらせるのがセオリーとなっているが、アイラ島の蒸留所は島中でよく採れるそのピートをふんだんに使用し、力強い独自の味わい事を生み出すという手段を選択した。
その産物がこの素晴らしい香りである。
どの蒸留所もピーティな香りの中にそれぞれの個性的な風味を持たせているアイラ・モルトだが、
特に私が部屋に常備していないと落ち着かないのがこちら。
LAPHROAIG(ラフロイグ)
10years old
10years old
アイラ・モルトの中でも一段とピーティな燻製香に、荒波を思わせる強烈な磯の香り、オイリーな舌触り、口に含んだ時の甘さが特徴となっている。
正直同じウイスキー好きでも、日本のものに慣れ親しんだ方なら苦手だという方も多い。
事実、10人に7人程の割合で「薬品臭い」「飲みもんじゃねぇ」という感想を頂戴する(笑)
好きか嫌いか、こんなに瞬時に明確に分かれる酒も珍しいかもしれない。
興味のある方は是非チャレンジしてみて欲しい。
これは余談ではあるが、ウイスキー、特にスコッチを飲む際におすすめの飲み方がある。
その名も「トゥワイスアップ」。
それはニート(ストレート)に同量の水を加えたもの。
要するに1:1の水割りなのだが、この場合グラスはチューリップ型のテイスティンググラスとなる。
ニートだとどうしてもアルコールのツンとした匂いが鼻に突き、香りを楽しむというよりも舌触りや味覚でのテイスティングとなってしまうのだが、スコッチの魅力はその"香り"の豊かさにある。
トゥワイスアップではその香り立ち、温度による変化までをも存分に楽しむ事ができるのだ。
バーボンのようにキレのある力強い香りの酒はロックにしてもその持ち味は変わる事は無いが、
スコッチの持つ繊細さを味わう事をしないのは本当に勿体無い。(値段も高いしw)
もしバーに行く機会があったら、是非この飲み方を試してみて欲しい。
その一杯で"ウイスキー"のイメージが変わる可能性も少なくは無いと思う。
P.S.
ちなみに居酒屋や"なんちゃって"バーで
「トゥワイスアップで!」なんて気取って言うと
「えっ?・・・・・なんですか?」と、赤っ恥をかくので注意が必要だ(笑)