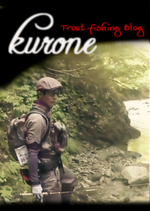2016年06月17日
「408」の癖がスゴイ話
♪Eagles - Desperado
御存じの通り、イーグルスは数多くの心に響くメロディを生み出してきた。
この曲はその中でも私が歩むべき道に迷いそうな時に昔から聴いてきた一曲。
ならず者——。
嘆きや憂いに寄り添う慈しみを感じさせる名曲。
グレン・フライの死から約半年。
年々好きなアーティストが一人、また一人と亡くなっていく。
かつての名手たちにも月日は平等に流れているから致し方無い事なのはわかってはいるが
なんとも寂しい限りだ。
———————————————————————————————
こんにちは!
最近ではすっかりアイコス芸人の仲間入りをしたくろねです(●゜ρ゜)y-゜゜
最初は独特の匂いや充電の手間に煩わしさを感じていましたが、
慣れてしまうとメリットの多さの方が勝ってきますね~。
”ヤニ”・”灰”からの解放は素晴らしいものがあります。
なんといっても喫煙時の嫁様の冷たい視線が気にならなくなったのが嬉しい(泣)
これも時代の流れですな。
さすがにくわえ煙草は出来ないので、釣りの最中は普通の煙草を吸いますけどね^^;
さてさて、今日は愛用し続けている”あの”リールの話をしようと思います。

Mitchell 408
以前その思い入れの強さや愛用に至った経緯については語らせて頂きましたが、
今回は機構面でもう少し掘り下げた話。
お使いの方は勿論ご存知の事ばかりとは思いますが、
オールドリールに興味はあってもいまいちどんな物なのかわからないという方へ
メンテナンスついでにご紹介していこうと思います。
まず裏面のカバーを開けると中はこんな感じ、

408特有の目の細かいスパイラルべベルギヤが確認できますね。
ミッチェルに限った話ではないですが、
この年代(1960年代)のリールは極めてシンプルな構造。
では早速分解してみましょう。

汚っ!(|||゜Α゜;;)
ここ最近めんどくさがってほったらかしでした。。ごめんなさい(笑)
クリーナーでキレイに洗うと、、

こんな感じです♪(*^^*)
構造がシンプルなだけあって、当然部品点数も少ないです。
ベアリング部を1つとして考えると、細かい物全部合わせても30数点。
さらにメンテナンスで分解する部分となると20程度と少ない為、
ものぐさな私でも頻繁にメンテナンスできます。
一般的にメンテナンスがし易いと言われるカージナル以上に単純な構造。
もしも現場でリールが壊れてしまった場合、
実際は時間が惜しくてサブのリールで対応してはいますが
部品さえあればその場で修理できる安心感が現代のリールとの違いですね。
あ、勿論世の中には現代の複雑なリールもあっさりと
分解メンテナンスされる方も沢山いらっしゃいます。
単純に、不器用な上忘れっぽい性格の私にはこれくらいの部品点数が限度なんです(笑)
ミッチェル408の特徴としてよく挙げられるのが、
・ハイスピード仕様のスパイラルべベルギヤ
・濃紺のボディと卵型シルエット
・巨大な足
・プラナマチックオシュレーションシステム
・アンチストッパ釣法(ランディング時のみストッパをかける)
――といったところですが、
今回はその中でもいまいちわかりづらい
『プラナマチックオシュレーションシステム』と
『アンチストッパ釣法の必要性』について
ざっくりですが説明をしてみようと思います。

”オシュレーションシステム”というのは、要するにスプールの上下動の機構の事。
ではそのプラナマチックとはなんぞや?ということですが、
言葉の意味は・・・
私に聞かれても困ります(ぇ
それはともかく、実際の動き方に関しては下の図にまとめてみました。

普通に波打つ周期で上下する通常のオシュレーション動作に対して、
プラナマチックでは上に行っては真ん中で留まり、下に行ってはまた真ん中で留まる。
この奇妙な動きのおかげで、スプールに巻かれた糸の形状は・・・

こんな具合に樽型になってしまいます。
いや、別に樽型になるからどーこーという話ではありませんが、
実はこの独特の動きがもたらしている効果の方がなんとも目からウロコなんです。
通常の摺動とは異なり、プラナマチックオシュレーションでは
一回の動作の度に中央付近で留まる影響で摺動の周期がスローになり
その結果密巻の状態になります。
密巻になるとそうでないものと比べ、
ライン放出時の摩擦によるロスが少ない為よく飛ぶらしいです。
しかし、ただ摺動をスローにしただけではライン同士が食い込み易くなってしまい、
キャスト時の思わぬトラブルの原因となってしまう。
※ラインの出が悪くていまいち飛ばなかったり、
変にラインがまとまって、ぼさぁっ!(゜Д゜゛)ノξ
と飛び出てしまうアレです。
そんなところまで考慮の上設計されているのがこのオシュレーションシステム。
中央付近の動きを抑えた分
上限(もしくは下限)へと向かう際には急速な動作となり、
部分的ではあるものの上下2段階の細やかな綾巻が構成される事で
ラインの食い込みを防いでいるんです。
そして実は、巻き上がりの樽のような形にもちゃんとメリットがあります。
丸いシルエットになることで、筒に巻くというよりは球状の物体を縛るような状態になり
よりテンションがかかった状態で巻き付けられる為ラインのズレが発生しづらいので
あのぼさぁっ!(゜Д゜゛)ノξが起こりづらいのです。
これがこのリールにおいて
「ストレスフリーに飛距離が出せる」
と言われている所以です。
現代のリールにはこの機構が採用されているものが無いので
実際の合理性はいか程なのかはなんとも言えませんが、
こんな優れた機構を半世紀も前に開発されていたという事自体驚きですね。
勤勉で研究熱心な日本人やドイツ人が作る物も精度の高さは勿論素晴らしいですが、
やはりフランスというお国柄なのか、発想のセンス自体がスゴイと思います。
———さて、次に「アンチストッパ釣法の必要性」について。
ミッチェルは正規の説明書にも
「ストッパはランディング時以外かけないで下さい」
というような内容が記されています。
一般的なリールを使っている方からすれば、そんなめんどくさい事する意味自体不明ですよね。(?ρ?)
カージナルだってそんな使い方をする人は見たことありません。
私自身最初の頃はそんな事気にせずにストッパをかけたまま”カリカリ”と音を出しながら使用していました。
しかしやはり必要だったのです。
ミッチェルのストッパ(ワンウェイ)の構造部はこんなんなっています。

このひよこのような可愛い部品のクチバシが
べベルギヤの裏に一体形成されたギザギザの部分に当たってストッパがかかる仕組み。
ストッパをかけるとこのロックポイントがずっとギヤ部に押し付けられている状態になり、
そのまま延々と使用していると気が付けばギヤのギザギザが丸くなってしまうんです。
最後はストッパが一切掛からない状態に・・・(|||゜∀゜)
身をもって体験しました・・はい(;π;)
素材自体が柔らかいので仕方の無い事なのでしょうが、ここはこのリールの一番の弱点な気がします。
中古の408を購入しても、結構な割合でこのギヤが摩耗している個体を見かけます。
とっくの昔に部品の生産も打ち切られているので、
この先も長く使いたいからこそ教科書通りの使用法を守らければと思いました。
でも実際に忙しない渓流の流れで、
ヒットしてから即座にストッパをかける事なんてできるのか?
A.——できるようになるんです(笑)
もちろん私もしばらくは慣れずに、
掛かった瞬間ハンドルが押し戻されて
ストッパをかける間もなく「びっくりバラシ」を多発しておりましたが、
今ではヒットの瞬間無意識のうちに左手薬指が勝手にストッパをかけてくれています。
人間、慣れるもんですね(^^;;)
不思議なもので、使い続ける事によって
年々自分の身体の一部のように馴染んでいくのを感じます。
今後も愛機408と共に沢山の思い出を刻んでいきたいと思います(=゚ω゚)ノ
ところで近況ですが、釣行はぼちぼちしております。
いつもの同僚との釣行、久々の兄との釣行等。
なかなか更新が捗らず申し訳有りませんが、
また面白いネタがありましたらどんどん更新していこうと思いますので宜しくお願いしますね♪(o^^o)
では今日はこの辺で(^ー^)ノ
御存じの通り、イーグルスは数多くの心に響くメロディを生み出してきた。
この曲はその中でも私が歩むべき道に迷いそうな時に昔から聴いてきた一曲。
ならず者——。
嘆きや憂いに寄り添う慈しみを感じさせる名曲。
グレン・フライの死から約半年。
年々好きなアーティストが一人、また一人と亡くなっていく。
かつての名手たちにも月日は平等に流れているから致し方無い事なのはわかってはいるが
なんとも寂しい限りだ。
———————————————————————————————
こんにちは!
最近ではすっかりアイコス芸人の仲間入りをしたくろねです(●゜ρ゜)y-゜゜
最初は独特の匂いや充電の手間に煩わしさを感じていましたが、
慣れてしまうとメリットの多さの方が勝ってきますね~。
”ヤニ”・”灰”からの解放は素晴らしいものがあります。
なんといっても喫煙時の嫁様の冷たい視線が気にならなくなったのが嬉しい(泣)
これも時代の流れですな。
さすがにくわえ煙草は出来ないので、釣りの最中は普通の煙草を吸いますけどね^^;
さてさて、今日は愛用し続けている”あの”リールの話をしようと思います。
Mitchell 408
以前その思い入れの強さや愛用に至った経緯については語らせて頂きましたが、
今回は機構面でもう少し掘り下げた話。
お使いの方は勿論ご存知の事ばかりとは思いますが、
オールドリールに興味はあってもいまいちどんな物なのかわからないという方へ
メンテナンスついでにご紹介していこうと思います。
まず裏面のカバーを開けると中はこんな感じ、
408特有の目の細かいスパイラルべベルギヤが確認できますね。
ミッチェルに限った話ではないですが、
この年代(1960年代)のリールは極めてシンプルな構造。
では早速分解してみましょう。
汚っ!(|||゜Α゜;;)
ここ最近めんどくさがってほったらかしでした。。ごめんなさい(笑)
クリーナーでキレイに洗うと、、
こんな感じです♪(*^^*)
構造がシンプルなだけあって、当然部品点数も少ないです。
ベアリング部を1つとして考えると、細かい物全部合わせても30数点。
さらにメンテナンスで分解する部分となると20程度と少ない為、
ものぐさな私でも頻繁にメンテナンスできます。
一般的にメンテナンスがし易いと言われるカージナル以上に単純な構造。
もしも現場でリールが壊れてしまった場合、
実際は時間が惜しくてサブのリールで対応してはいますが
部品さえあればその場で修理できる安心感が現代のリールとの違いですね。
あ、勿論世の中には現代の複雑なリールもあっさりと
分解メンテナンスされる方も沢山いらっしゃいます。
単純に、不器用な上忘れっぽい性格の私にはこれくらいの部品点数が限度なんです(笑)
ミッチェル408の特徴としてよく挙げられるのが、
・ハイスピード仕様のスパイラルべベルギヤ
・濃紺のボディと卵型シルエット
・巨大な足
・プラナマチックオシュレーションシステム
・アンチストッパ釣法(ランディング時のみストッパをかける)
――といったところですが、
今回はその中でもいまいちわかりづらい
『プラナマチックオシュレーションシステム』と
『アンチストッパ釣法の必要性』について
ざっくりですが説明をしてみようと思います。
”オシュレーションシステム”というのは、要するにスプールの上下動の機構の事。
ではそのプラナマチックとはなんぞや?ということですが、
言葉の意味は・・・
私に聞かれても困ります(ぇ
それはともかく、実際の動き方に関しては下の図にまとめてみました。
普通に波打つ周期で上下する通常のオシュレーション動作に対して、
プラナマチックでは上に行っては真ん中で留まり、下に行ってはまた真ん中で留まる。
この奇妙な動きのおかげで、スプールに巻かれた糸の形状は・・・

こんな具合に樽型になってしまいます。
いや、別に樽型になるからどーこーという話ではありませんが、
実はこの独特の動きがもたらしている効果の方がなんとも目からウロコなんです。
通常の摺動とは異なり、プラナマチックオシュレーションでは
一回の動作の度に中央付近で留まる影響で摺動の周期がスローになり
その結果密巻の状態になります。
密巻になるとそうでないものと比べ、
ライン放出時の摩擦によるロスが少ない為よく飛ぶらしいです。
しかし、ただ摺動をスローにしただけではライン同士が食い込み易くなってしまい、
キャスト時の思わぬトラブルの原因となってしまう。
※ラインの出が悪くていまいち飛ばなかったり、
変にラインがまとまって、ぼさぁっ!(゜Д゜゛)ノξ
と飛び出てしまうアレです。
そんなところまで考慮の上設計されているのがこのオシュレーションシステム。
中央付近の動きを抑えた分
上限(もしくは下限)へと向かう際には急速な動作となり、
部分的ではあるものの上下2段階の細やかな綾巻が構成される事で
ラインの食い込みを防いでいるんです。
そして実は、巻き上がりの樽のような形にもちゃんとメリットがあります。
丸いシルエットになることで、筒に巻くというよりは球状の物体を縛るような状態になり
よりテンションがかかった状態で巻き付けられる為ラインのズレが発生しづらいので
あのぼさぁっ!(゜Д゜゛)ノξが起こりづらいのです。
これがこのリールにおいて
「ストレスフリーに飛距離が出せる」
と言われている所以です。
現代のリールにはこの機構が採用されているものが無いので
実際の合理性はいか程なのかはなんとも言えませんが、
こんな優れた機構を半世紀も前に開発されていたという事自体驚きですね。
勤勉で研究熱心な日本人やドイツ人が作る物も精度の高さは勿論素晴らしいですが、
やはりフランスというお国柄なのか、発想のセンス自体がスゴイと思います。
———さて、次に「アンチストッパ釣法の必要性」について。
ミッチェルは正規の説明書にも
「ストッパはランディング時以外かけないで下さい」
というような内容が記されています。
一般的なリールを使っている方からすれば、そんなめんどくさい事する意味自体不明ですよね。(?ρ?)
カージナルだってそんな使い方をする人は見たことありません。
私自身最初の頃はそんな事気にせずにストッパをかけたまま”カリカリ”と音を出しながら使用していました。
しかしやはり必要だったのです。
ミッチェルのストッパ(ワンウェイ)の構造部はこんなんなっています。
このひよこのような可愛い部品のクチバシが
べベルギヤの裏に一体形成されたギザギザの部分に当たってストッパがかかる仕組み。
ストッパをかけるとこのロックポイントがずっとギヤ部に押し付けられている状態になり、
そのまま延々と使用していると気が付けばギヤのギザギザが丸くなってしまうんです。
最後はストッパが一切掛からない状態に・・・(|||゜∀゜)
身をもって体験しました・・はい(;π;)
素材自体が柔らかいので仕方の無い事なのでしょうが、ここはこのリールの一番の弱点な気がします。
中古の408を購入しても、結構な割合でこのギヤが摩耗している個体を見かけます。
とっくの昔に部品の生産も打ち切られているので、
この先も長く使いたいからこそ教科書通りの使用法を守らければと思いました。
でも実際に忙しない渓流の流れで、
ヒットしてから即座にストッパをかける事なんてできるのか?
A.——できるようになるんです(笑)
もちろん私もしばらくは慣れずに、
掛かった瞬間ハンドルが押し戻されて
ストッパをかける間もなく「びっくりバラシ」を多発しておりましたが、
今ではヒットの瞬間無意識のうちに左手薬指が勝手にストッパをかけてくれています。
人間、慣れるもんですね(^^;;)
不思議なもので、使い続ける事によって
年々自分の身体の一部のように馴染んでいくのを感じます。
今後も愛機408と共に沢山の思い出を刻んでいきたいと思います(=゚ω゚)ノ
ところで近況ですが、釣行はぼちぼちしております。
いつもの同僚との釣行、久々の兄との釣行等。
なかなか更新が捗らず申し訳有りませんが、
また面白いネタがありましたらどんどん更新していこうと思いますので宜しくお願いしますね♪(o^^o)
では今日はこの辺で(^ー^)ノ
〜Fin〜